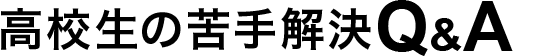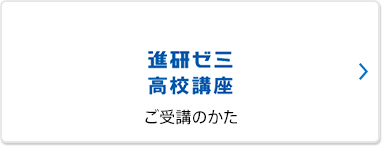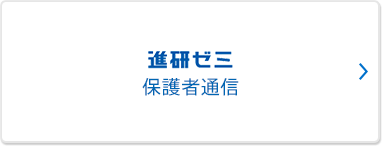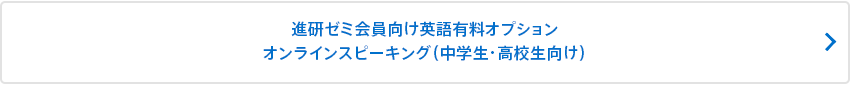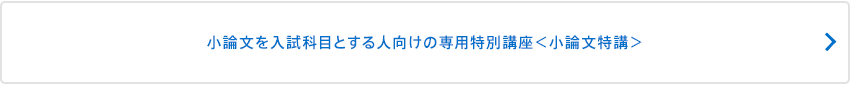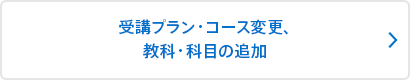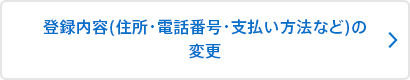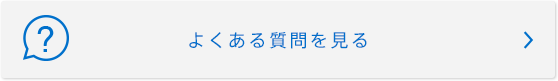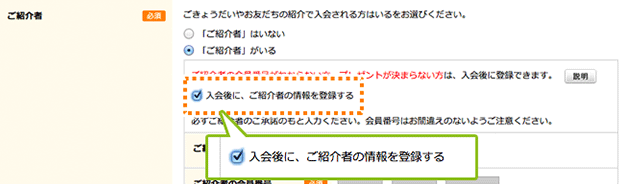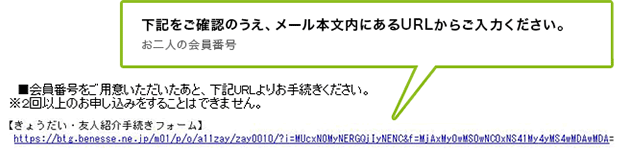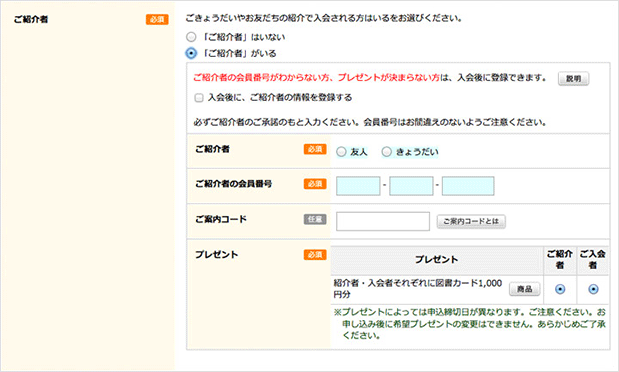正弦定理の基本と使い方を例題でマスター
正弦定理の基本と使い方
正弦定理の基本と使い方を教えてください。
進研ゼミからの回答!
正弦定理とは
正弦定理の基本と使い方について、例題を使いながらご説明しますね。
正弦定理は、三角形の辺の長さと角のサイン(sin)の間に成り立つ便利な定理です。具体的には、以下のようになります。
三角形ABCにおいて、各辺の長さをそれぞれa, b, cとし、それぞれの辺の対角の大きさをA, B, Cとすると、
a / sinA = b / sinB = c / sinC = 2R
が成り立ちます。ここで、Rは三角形ABCの外接円の半径です。
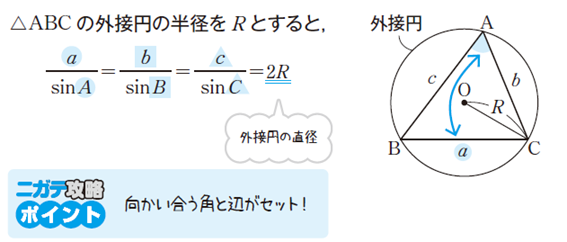
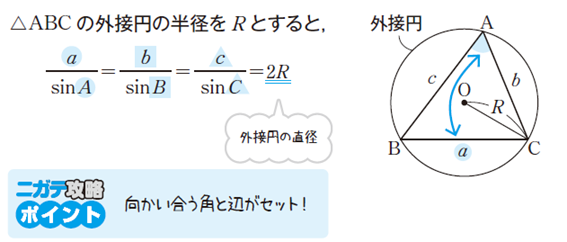
つまり、
・(辺の長さ) / (その対角のサイン) は、どの辺と角の組み合わせでも一定の値になる
・その値は、外接円の直径に等しい
ということです。
正弦定理は、どんなときに使える?
正弦定理は、主に以下の3つの場合に使えます。
1.三角形の辺の長さを求める
・2つの角の大きさと、1つの辺の長さがわかっているとき
2.三角形の角の大きさを求める
・2つの辺の長さと、1つの対角の大きさがわかっているとき
3.三角形の外接円の半径を求める
・辺の長さと、その対角の大きさが1組わかっているとき
正弦定理の使い方を例題で確認
では実際に正弦定理を使って例題を解いてみましょう。
例題1:辺の長さを求める
三角形ABCにおいて、b= 2,∠B = 45°, ∠C = 60 °のとき、辺cの長さを求めよ。
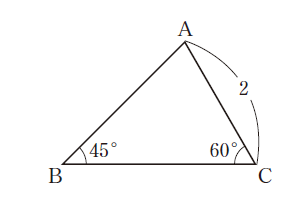
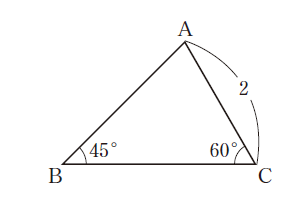
考え方
・わかっている情報:2つの角(∠B, ∠C)と1つの辺(b)
・求めたいもの:辺cの長さ
・使う定理:正弦定理
解答
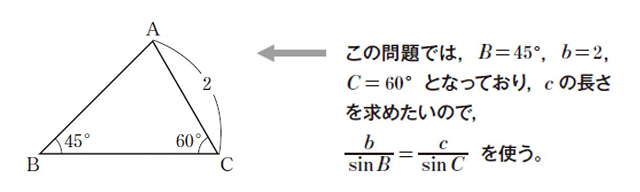
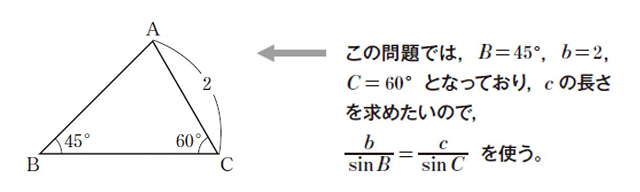
正弦定理より、
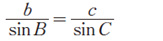
ここに、わかっている値を代入します。
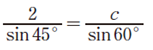
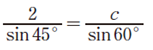
両辺にsin60°をかけます。
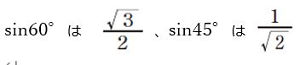
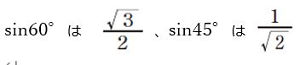
なので、
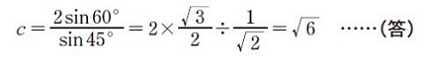
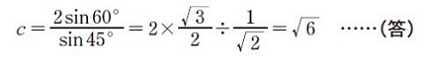
したがって、辺cの長さは√6です。
ポイント
• 正弦定理を使う際は、どの辺と角の組み合わせを使うかを見極めることが重要です。
例題2:1つの辺と、外接円の半径を求める
三角形ABCにおいて、a = 8, ∠A = 30°, ∠C = 135°のとき、cと外接円の半径Rの大きさを求めなさい。
考え方
・わかっている情報:2つの角(∠A, ∠C)と1つの辺(a)
・求めたいもの:c、外接円の半径R
・使う定理:正弦定理
解答
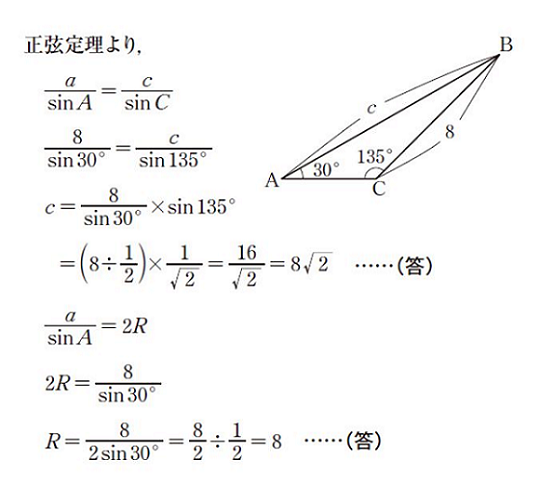
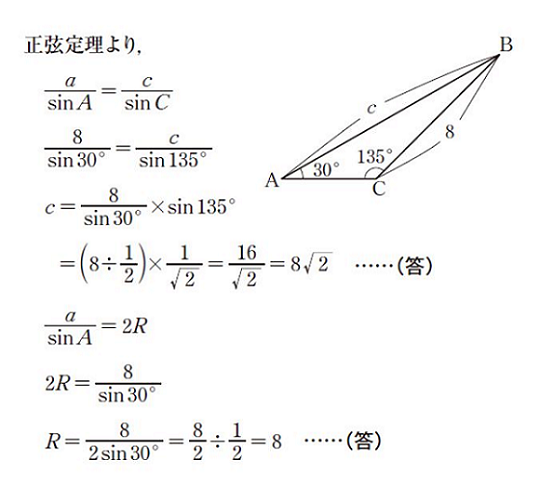
まとめ
正弦定理は、三角形の辺の長さと角のサインを結びつける便利な公式です。
・(辺の長さ) / (その対角のサイン) = 2R(外接円の直径)
この関係を理解し、例題を通して使い方をマスターすることで、さまざまな三角形の問題を解くことができるようになります。
分母と分子の対応に注意しながら、正弦定理を使いこなしましょう!
それではこれで回答を終わります。これからも『進研ゼミ高校講座』で確実に力をつけていってくださいね。
 数学のQ&Aランキング
数学のQ&Aランキング
- 【数列】Σの和の求め方
- 【関数と極限】∞+∞=∞とは
- 【三角関数】0<θ<π/4 の角に対する三角関数での表し方
- 【指数・対数関数】1/√aを(1/a)^r の形になおす方法
- 【図形と計量】180°-θの三角比
 全体のQ&Aランキング
全体のQ&Aランキング
- 【動名詞】①<make + O + C >構文の訳し方②間接疑問文における疑問詞の訳し方
- 【数列】Σの和の求め方
- 【関数と極限】∞+∞=∞とは
- 【三角関数】0<θ<π/4 の角に対する三角関数での表し方
- 【指数・対数関数】1/√aを(1/a)^r の形になおす方法
 「数と式」Q&A一覧
「数と式」Q&A一覧
- 【数と式】「pならばq 」が真のとき,集合Pが集合Qに含まれる理由
- 【数と式】たすきがけのやり方について
- 【数と式】たすきがけはいつ使うのか
- 【数と式】ルートの中が「負の数の2乗」のときの,ルートのはずし方
- 【数と式】因数分解のしかた
- 【数と式】因数分解の式の整理について
- 【数と式】因数分解の式変形について
- 【数と式】因数分解をするときの途中式について
- 【数と式】対称式はどんなとき使うんですか?
- 【数と式】式変形するときの文字の置き換え方
- 【数と式】必要条件・十分条件
- 【数と式】文字を含む式の書き方
- 【数と式】無理数の整数部分,小数部分の求め方
- 【数と式】絶対値と場合分け
- 【数と式】絶対値記号の意味
- 【数と式】絶対値記号を含む方程式・不等式の解き方
- 【数と式】負の値の絶対値の考え方について
- 【数と式】逆・裏・対偶の関係
- 【数と式】連立不等式の解の求め方
- 【数と式】2重根号の計算
- 【数と式】有理数ってどんな数?分数で表せる数の見分け方と無理数との違いが知りたい
- 【数と式】無理数ってどんな数?有理数との違いや身近な例も知りたい